高校化学で特に重要な工業的製法は5つあります.
そのうちの1つであるアンモニアソーダ法は炭酸ナトリウム$\mrm{Na_2CO_3}$の製法で,主な原料は食塩$\mrm{NaCl}$です.アンモニアソーダ法は
炭酸カルシウム$\mrm{CaCO_3}$ → 二酸化炭素$\mrm{CO_2}$ → 炭酸水素ナトリウム$\mrm{NaHCO_3}$ → 炭酸ナトリウム$\mrm{Na_2CO_3}$
という流れで炭酸ナトリウム$\mrm{Na_2CO_3}$をつくります.
アンモニアソーダ法のポイントは副生成物が多く,それらを再利用することで無駄の少ない製法になっている点です.
アンモニアソーダ法は特に重要な5つの工業的製法の中でも,多くの知識が必要で複雑です.それだけに試験でも狙われやすいので,確実に押さえたい製法です.
なお,アンモニアソーダ法はベルギーのエルネスト・ソルベー氏が開発した製法でソルベー法ということもあります.
ガスバーナー程度しか使わない「実験室的製法」に対して,「工業的製法」はビジネス用の製法で利益の上がるように物質を作るのが目標です.そのため「無駄なく,安くを目指した製法」となっており,ガンガン圧力をかけたり,高温にすることができるのも特徴です.
「工業的製法」の一連の記事
アンモニアソーダ法の流れ
アンモニアソーダ法で必要なものは
- 塩化ナトリウム(食塩)$\mrm{NaCl}$
- 水$\mrm{H_2O}$
- アンモニア$\mrm{NH_3}$
- 炭酸カルシウム(石灰石)$\mrm{CaCO_3}$
です.アンモニアソーダ法は
- 炭酸ナトリウム$\mrm{Na_2CO_3}$をつくるステップ
- 副生成物を再利用するステップ
の2つに分けて理解すると整理しやすいでしょう.
まずは簡単に流れを説明します.
炭酸ナトリウムを作るステップ
最終的にアンモニアソーダ法の反応をまとめた式は
なのですが,実際に食塩$\mrm{NaCl}$と炭酸カルシウム(石灰石)$\mrm{CaCO_3}$を混ぜてもこの反応は起こりません.
しかし,仲介役としてアンモニア$\mrm{NH_3}$を登場させることで,最終的にこの反応と同じことを起こすことができます.
この反応の流れは
- 炭酸カルシウム$\mrm{CaCO_3}$を加熱して,二酸化炭素$\mrm{CO_2}$をつくる.
- 塩化ナトリウム(食塩)$\mrm{NaCl}$,水$\mrm{H_2O}$,アンモニア$\mrm{NH_3}$,二酸化炭素$\mrm{CO_2}$を反応させて,炭酸水素ナトリウム$\mrm{NaHCO_3}$をつくる.
- 炭酸水素ナトリウム$\mrm{NaHCO_3}$を加熱して,炭酸ナトリウム$\mrm{Na_2CO_3}$をつくる.
です.
副生成物を再利用するステップ
工業的製法はいわば「ビジネス的製法」ですから無駄なく安くが基本です.そのため,副生成物はできるだけ少なくしたいところです.
しかし,上の反応だけでは副生成物として
- 酸化カルシウム(生石灰)$\mrm{CaO}$
- 塩化アンモニウム$\mrm{NH_4Cl}$
が生成し無駄が生じます.
そこで,次のような流れで酸化カルシウム(生石灰)$\mrm{CaO}$と塩化アンモニウム$\mrm{NH_4Cl}$を処理します.
- 酸化カルシウム(生石灰)$\mrm{CaO}$に水$\mrm{H_2O}$を加えて,水酸化カルシウム$\mrm{Ca(OH)_2}$をつくる.
- 塩化アンモニウム$\mrm{NH_4Cl}$と水酸化カルシウム$\mrm{Ca(OH)_2}$を混ぜて,水$\mrm{H_2O}$,アンモニア$\mrm{NH_3}$,塩化カルシウム$\mrm{CaCl_2}$をつくる.
これにより出てきた水$\mrm{H_2O}$とアンモニア$\mrm{NH_3}$は再利用できるので,捨てるものが減り無駄が削減されました.
ステップ1:炭酸ナトリウム$\mrm{Na_2CO_3}$をつくる
まずは,炭酸ナトリウム$\mrm{Na_2CO_3}$をつくります.
二酸化炭素$\mrm{CO_2}$をつくる
炭酸カルシウム(石灰石)$\mrm{CaCO_3}$を加熱すると,二酸化炭素$\mrm{CO_2}$と酸化カルシウム(生石灰)$\mrm{CaO}$に熱分解することは知っておきたいところです.
この「炭酸ナトリウム$\mrm{Na_2CO_3}$を作るステップ」では二酸化炭素$\mrm{CO_2}$の方が重要です.
炭酸水素ナトリウム$\mrm{NaHCO_3}$をつくる
炭酸水素ナトリウム$\mrm{NaHCO_3}$は塩化ナトリウム(食塩)$\mrm{NaCl}$,水$\mrm{H_2O}$,アンモニア$\mrm{NH_3}$,二酸化炭素$\mrm{CO_2}$を反応させれば発生します.
ただし,混ぜ方が実は問題で次のように順に混ぜるのがポイントです.
- 水$\mrm{H_2O}$に食塩$\mrm{NaCl}$を溶かして,食塩水$\mrm{NaCl}aq$をつくる.
- アンモニア$\mrm{NH_3}$は水によく溶けることを利用して,食塩水$\mrm{NaCl}aq$にアンモニア$\mrm{NH_3}$を吸収させる.
- アンモニア$\mrm{NH_3}$を溶かしたことにより塩基性になるので,二酸化炭素$\mrm{CO_2}$で中和させることができる.
二酸化炭素$\mrm{CO_2}$を水$\mrm{H_2O}$に溶かした炭酸$\mrm{H_2CO_3}$が酸性なので,手順3で中和が起きるというわけですね.
「アンモニアソーダ法」という名前は,このステップでアンモニア$\mrm{NH_3}$と炭酸(ソーダ)$\mrm{H_2CO_3}$が登場するところからきています.
炭酸ナトリウム$\mrm{Na_2CO_3}$をつくる
炭酸ナトリウム$\mrm{Na_2CO_3}$は炭酸水素ナトリウム$\mrm{NaHCO_3}$の熱分解により生じることは,中学校で習った記憶がある人も多いと思います.
この分解は1つの化学反応で固体,液体,気体が発生しているという点で特徴的ですね.
一度まとめる
さて,いま出てきた3つの反応式をみます.
この3つの反応式について,(1)+2×(2)+(3)とすることで
が得られますね.
さて,反応式(4)をみると目的の炭酸ナトリウム$\mrm{Na_2CO_3}$が出来ているので一応は成功です.
ステップ2:副生成物を再利用する
先ほども書いたように工業的製法は「無駄なく安く」が基本ですから,
で終わりとしては,副生成物の酸化カルシウム(生石灰)$\mrm{CaO}$と塩化アンモニウム$\mrm{NH_4Cl}$が無駄となっています.
そこで,酸化カルシウム(生石灰)$\mrm{CaO}$と塩化アンモニウム$\mrm{NH_4Cl}$をうまく再利用して無駄を減らしましょう.
酸化カルシウム(生石灰)$\mrm{CaO}$を処理する
アンモニアソーダ法では酸化カルシウム$\mrm{CaO}$に水$\mrm{H_2O}$を加えて,水酸化カルシウム$\mrm{Ca(OH)_2}$をつくります.
ここでは,アルカリ金属,アルカリ土類金属の酸化物($\mrm{Na_2O}$, $\mrm{BaO}$, $\mrm{CaO}$など)に水$\mrm{H_2O}$を加えると,水酸化物($\mrm{NaOH}$, $\mrm{Ba(OH)_2}$, $\mrm{Ca(OH)_2}$など)になることを利用しています.
この反応は頻出なので,忘れていた人は確認しておきたいところです.
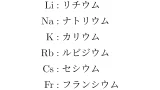
塩化アンモニウム$\mrm{NH_4Cl}$を処理する
塩化アンモニウム$\mrm{NH_4Cl}$からアンモニア$\mrm{NH_3}$を引き剥がすことができれば,アンモニア$\mrm{NH_3}$を再利用できますね.
今つくった水酸化カルシウム$\mrm{Ca(OH)_2}$と塩化アンモニウム$\mrm{NH_4Cl}$を反応させると,次の反応によりアンモニアが発生します.
一度まとめる
さて,いま出てきた2つの反応式をみます.
について,(5)+(6)とすることで,
を得ます.
これにより塩化アンモニウム$\mrm{NH_4Cl}$と酸化カルシウム(生石灰)$\mrm{CaO}$から,アンモニア$\mrm{NH_3}$を引き剥がすことに成功し,副生成物は塩化カルシウム$\mrm{CaCl_2}$だけになりました.
全てまとめる
さて,炭酸ナトリウム$\mrm{Na_2CO_3}$をつくり,副生成物も処理したところで全ての式をまとめましょう.
炭酸ナトリウムをつくる反応式(4)と副生成物を処理する反応式(7)を思い出しましょう.
これらについて,(4)+(7)とすれば,
となり,全体の反応式が得られます.
補足
アンモニアソーダ法では反応式(2)で使ったアンモニアを反応式(6)で全量回収でき,アンモニアを循環させるだけで新たにアンモニアを必要とせず,棄てることもない点には注目しておきましょう.
また,副生成物の塩化カルシウム$\mrm{CaCl_2}$は道路の凍結防止剤などに用いられることがありますが,用途はあまり多くありません.
そこで,あえてアンモニア$\mrm{NH_3}$を回収せず,化学肥料として重要な塩化アンモニウム$\mrm{NH_4Cl}$を取り出すこともあります.


コメント