2018年度の京都大学の前期入試の理系数学を全問(問1〜問6)解説します.
各問を考え方から解説しています.
「大学入試数学解説」の一連の記事
第1問
0でない実数$a$, $b$, $c$は次の条件(i)と(ii)を満たしながら動くものとする.
(i) $1+c^{2}\leqq2a$.
(ii) 2つの放物線$C_{1}:y=ax^{2}$と$C_{2}:y=b(x-1)^{2}+c$は接している.
ただし,2つの曲線が接するとは,ある共有点において共通の接線をもつことであり,その共有点を接点という.
- $C_{1}$と$C_{2}$の接点の座標を$a$と$c$を用いて表せ.
- $C_{1}$と$C_{2}$の接点が動く範囲を求め,その範囲を図示せよ.
図形と方程式の問題ですね.
解答への筋道
(1)は基本問題なので確実に解きたい問題で(2)が本番です.
問題の捉え方
実数$a$, $b$, $c$を好きにとると曲線$C_1$, $C_2$は必ずしも接しませんが,うまく実数$a$, $b$, $c$を動かすことで
- $a$:放物線$C_1$の広がり方
- $b$:放物線$C_2$の広がり方
- $c$:放物線$C_2$の$y$軸方向の位置
をコントロールすることができますから,うまく調節すれば曲線$C_1$, $C_2$が接するようにできそうです.
このように曲線$C_1$, $C_2$が接するときを考えるというのが条件(ii)ですね.
また,条件(i)$1+c^{2}\leqq2a$から$a$に対して$c$はあまり大きくも小さくもなれませんから,放物線$C_{2}$の上下の動きにも制限があることに注意しましょう.
求める領域
(1)で接点の座標は$\Bigl(\dfrac{c}{a},\dfrac{c^{2}}{a}\Bigr)$と求められます.これより$(X,Y)=\Bigl(\dfrac{c}{a},\dfrac{c^{2}}{a}\Bigr)$の動く範囲を求めればよいですね.
このとき,$a$, $c$は
と表すことができ,これを条件(ii)の$1+c^{2}\leqq2a$に代入して整理すると
となります.
しかし,この問題の状況設定では放物線の軸である$X=0,1$で接することはありませんから,これらを併せた
が求める領域となりそうです.このように,接点が動かない範囲は除外して答えないといけないところは見落としてしまいそうなので注意してください.
以下の解答では,同値変形で接点が動く範囲を求めています.
解答例
$f(x)=ax^{2}$, $g(x)=b(x-1)^{2}+c$とおく.
(1) 接点の座標を$(t,at^2)$とおく.曲線$C_{1}$, $C_{2}$の$x=t$での接線はそれぞれ
である.よって,条件(ii)は
と同値である.よって,$a\neq0$に注意して接点の座標は$\Bigl(\dfrac{c}{a},\dfrac{c^{2}}{a}\Bigr)$である.
(2) (1)より,点$(X,Y)$が求める領域上の点であることと,
を満たす0でない実数$a$, $b$, $c$が存在することは同値である.$c\neq0$に注意して
だから,これを$(*)$の第2式に代入して整理すると
であり,第3式に代入して整理すると
である.$c\neq0$より$Y=\dfrac{c^{2}}{a}\neq0$だから,$(**)$を満たす0でない実数$b$が存在するためには
が必要十分である.
よって,$(*)$を満たす0でない実数$a$, $b$, $c$が存在することと,$(X,Y)$が
を満たすことは同値である.よって,その範囲は下図の領域のようになる.
ただし,点$(1,1)$と直線$x=0$上の点は含まず,点$(1,1)$以外の境界は全て含む.
第2問
$n^{3}-7n+9$が素数となるような整数$n$を全て求めよ.
京都大学では頻出の素数が絡んだ整数問題ですね.
解答への筋道1
整数問題では具体的に整数を代入して実験することはとても大切です.また,素数かどうかを判定するには,割った余りを考えるのがよくある方法です.
問題の捉え方
具体的な整数$n$でいくつか実験すると
- $n=-3$のとき,$n^{3}-7n+9=3$
- $n=-2$のとき,$n^{3}-7n+9=15$
- $n=-1$のとき,$n^{3}-7n+9=15$
- $n=0$のとき,$n^{3}-7n+9=9$
- $n=1$のとき,$n^{3}-7n+9=3$
- $n=2$のとき,$n^{3}-7n+9=3$
- $n=3$のとき,$n^{3}-7n+9=15$
となり,たとえば$n=-3,1,2$で条件を満たすことが分かります.
この他にも素数となることがないかを考えるわけですが,今の実験から$n^{3}-7n+9$は3の倍数となることが予想できますね.
よって,この予想が正しければ$n^{3}-7n+9$が素数となるには,$n^{3}-7n+9=3$となるしかないことが分かりますね.
また,$n^{3}-7n+9$は$n$の3次式なので,$n$が大きければ3よりも大きくなり,$n$が小さければ負となるので,$n^{3}-7n+9=3$となる整数$n$は0の近くにしかなさそうですね.
倍数であることの証明
一般に整数$m$の倍数であることを証明するためには,$m$を法として$\equiv0$となることを示せばよいですね.
本問では3を法として$n^{3}-7n+9\equiv0$となることを示すことになります.
合同式を知らない人も$n=3k$, $n=3k+1$, $n=3k-1$($k$は整数)などと場合分けして考えても構いません.
なお,3を法とした場合は$n^3\equiv n$となるので,このことを知っておくと
となって見通し良く$n^{3}-7n+9\equiv0$となることが分かりますね.
しかし,答案で証明なしにこの事実を使うのは怖いので,$n\equiv-1,0,1$のそれぞれで計算して$n^{3}-7n+9\equiv0$を示すのが無難でしょう.
解答例1
3を法とする.
- $n\equiv-1$のとき
- $n\equiv0$のとき
- $n\equiv1$のとき
となるから,任意の自然数$n$に対して$n^{3}-7n+9$は3の倍数である.
よって,$n^{3}-7n+9$が素数となることと$n^{3}-7n+9=3$は必要十分である.よって,
だから,求める整数$n$は$-3,1,2$である.
解答への筋道2
3の倍数であることを示すために,連続3整数の積に持ち込む方法もあります.一般に次が成り立ちます.
$N$個の連続する自然数の積は$N$の倍数である.
$N$個の連続自然数の中には必ず$N$の倍数が存在するので,この定理が成り立つことが分かりますね.
なお,本問では用いませんが,より強く次が成り立つことも知っておいてよいでしょう.
$N$個の連続する自然数の積は$N!$の倍数である.
$k\geqq N$なる任意の整数$k$に対して,組み合わせ$\Co{k}{N}$は
だから,分母を払って$\Co{k}{N}\cdot N!=k(k-1)(k-2)\dots(k-N+1)$である.
$\Co{k}{N}$は整数だから,連続$N$整数の積$k(k-1)(k-2)\dots(k-N+1)$は$N!$の倍数である.
解答例2
任意の整数$n$に対して
である.$n-1$, $n$, $n+1$は連続3整数だからいずれかは3の倍数なので,第1項$(n-1)n(n+1)$は3の倍数となります.
また,第2項$3(-2n+3)$も3の倍数だから,結局$n^{3}-7n+9$も3の倍数である.(以下同様)
第3問
$\alpha$は$0<\alpha\leqq\dfrac{\pi}{2}$を満たす定数とし,四角形$\mrm{ABCD}$に関する次の2つの条件を考える.
(i) 四角形$\mrm{ABCD}$は半径1の円に内接する.
(ii) $\ang{ABC}=\ang{DAB}=\alpha$
条件(i)と(ii)を満たす四角形のなかで,4辺の長さの積
が最大となるものについて,$k$の値を求めよ.
最後には$k$の最大値を求めることになりますが,メインは平面図形の問題です.
解答への筋道
四角形$\mrm{ABCD}$が半径1の外接円が決まっていることから,正弦定理を思い付けるかが初手のキーポイントです.
問題の捉え方
本問では,$\alpha$を$0<\alpha\leqq\dfrac{\pi}{2}$に固定した状態で,四角形$\mrm{ABCD}$が条件(i)と条件(ii)を満たしながら変化します.
イメージとしては,$\ang{ABC}$と$\ang{DAB}$を$\alpha$に固定したまま辺$\mrm{AB}$を左右にスライドさせるとき,どの位置に辺$\mrm{AB}$があるときに四角形
の面積が最大になるか,という問題なわけです.
ただし,辺$\mrm{AB}$はどのようにでもスライドさせられるわけではなく,どこかの辺の長さが0に潰れしまわないように動かさないといけないことに注意が必要です.
正弦定理
「外接円の半径」というワードを見たとき,瞬時に正弦定理を第一候補として思い付きたいところです.
正弦定理を使うとなると三角形を考える必要がありますから,対角線$\mrm{AC}$を引いて,$\theta=\ang{CAB}$などとおきたいところです.
ここで正弦定理を用いれば$\mrm{AB}$, $\mrm{BC}$, $\mrm{C D}$, $\mrm{DA}$の長さが$\alpha$と$\theta$で表せるので,$k$も$\alpha$と$\theta$で表せますね.
積和の公式
$\theta=\ang{CAB}$とおいたときの$k$は
となります.このまま単純に$\theta$について微分して増減を調べることによっても最大値は求まりますが,もう少し$\theta$について見通しよく変形したいところです.
積和の公式を使うと,
が成り立ち,$k=8\bra{\cos{2\theta}-\cos{2\alpha}}\sin^2{\theta}$となりますね.
このように,三角関数の積について
- $\sin(X+\alpha)\sin(X-\beta)$
- $\sin(X+\alpha)\cos(X-\beta)$
といった形をしている場合は,積和の公式を用いることで変数がまとめられて見通しがよくなることは多くあります.
変数$\theta$は$\cos{2\theta}$と$\sin^2{\theta}$の2ヶ所に現れているので,2倍角の公式$\cos{2\theta}=1-2\sin^2{\theta}$を用いると,$\sin{\theta}$の関数として$k$を表すことができますね.
解答例
$\theta=\ang{CAB}$とおく.$\tri{ABC}$の内角の和が$180^\circ$だから
である.また,四角形$\mrm{ABCD}$は円に内接するから$\ang{CDA}=\pi-\ang{CBA}=\pi-\alpha$となるので,$\tri{CDA}$の内角の和が$180^\circ$であることと併せて
である.
外接円の半径は1だから,正弦定理より,
だから,
を得る.ただし,最後から3つ目の等号で積和の公式を,最後から2つ目の等号で2倍角の公式を用いた.
ここで,$t=\sin^2{\theta}$とする.$\theta$は$0<\theta<\alpha$の範囲をくまなく動き,仮定から$\alpha$は$0<\alpha\leqq\dfrac{\pi}{2}$なる実数なので,$t$は$0<t<\sin^2{\alpha}$の範囲をくまなく動く.
だから$t=\dfrac{\sin^2{\alpha}}{2}$で$k$は最大値$4\sin^4{\alpha}$をとる.
第4問
コインを$n$回投げて複素数$z_{1}$, $z_{2}$, $\dots$, $z_{n}$を次のように定める.
(i) 1回目に表が出れば$z_{1}=\dfrac{-1+\sqrt{3}i}{2}$とし,裏が出れば$z_{1}=1$とする.
(ii) $k=2$, 3, $\dots$, $n$のとき,$k$回目に表が出れば$z_{k}=\dfrac{-1+\sqrt{3}i}{2}z_{k-1}$とし,裏が出れば$z_{k}=\overline{z_{k-1}}$とする.ただし,$\overline{z_{k-1}}$は$z_{k-1}$の共役複素数である.
このとき,$z_{n}=1$となる確率を求めよ.
問題設定は複素数ですが,メインは確率です.
解答への筋道
複素数$z_{k}$は$z_{k-1}$とコインの出方で決まるので,京都大学では頻出の確率漸化式の問題ですね.
問題の捉え方
$\alpha=\dfrac{-1+\sqrt{3}i}{2}$を極形式で表すと
なので,$\alpha$をかけることで複素平面上の点の原点中心・偏角$\dfrac{2\pi}{3}$の回転が起こります.
また,コインが裏のときは共役複素数に移すことになるので,実軸に関する対称移動が起こります.
このことから$z_k$は複素平面上の3点$(1,0)$, $(\cos{\frac{2\pi}{3}},\sin{\frac{2\pi}{3}})$, $(\cos{\frac{2\pi}{3}},-\sin{\frac{2\pi}{3}})$を移ることが分かりますね.
確率漸化式
$z_k$は$z_{k-1}$から帰納的に定まります.このように,帰納的に状況が定まる問題では確率漸化式の考え方を用いるのが定石です.
確率漸化式の問題ではどのような場合があるかを考え,それぞれの場合の確率に関して漸化式を考えるのが基本です.
本問では$z_k$が複素平面上の3点$\mrm{A}$, $\mrm{B}$, $\mrm{C}$のそれぞれに存在する確率$P_k$, $Q_k$, $R_k$の漸化式を作ることになります.
また,確率漸化式を考える際には「全ての確率の和が1」という情報も大切になることが忘れないように注意してください.
解答例
$\alpha=\dfrac{-1+\sqrt{3}i}{2}$とすると,
だから,コインが表なら$z_{k}$は$z_{k-1}$が表す複素平面上の点を原点中心・偏角$\dfrac{2\pi}{3}$回転させた点を表す複素数である.
一方,コインが裏なら$z_{k}$は$z_{k-1}$が表す複素平面上の点を実軸に関して対称移動させた点を表す複素数である.
よって,$k=1,2,\dots,n$に対して,$z_{k}$は$1(=\alpha^{0})$, $\alpha$, $\alpha^{2}$のいずれかに一致する.
ここで,$k=1,2,\dots,n$に対して,$z_{k}=1,\alpha,\alpha^{2}$となる確率をそれぞれ$P_{k}$, $Q_{k}$, $R_{k}$とする.
表が出て$z_{k+1}$が定まる場合と裏が出て$z_{k+1}$が定まる場合を考えれば,
が成り立つ.$(*)$と自明な等式$P_{k}+Q_{k}+R_{k}=1$を併せて,
を得る.また,式$(*)$と$(**)$から$k=2,3,\dots,n$に対して$P_{k}=Q_{k}$が成り立ち,また$P_{1}=\dfrac{1}{2}=Q_{1}$も成り立つ.
以上より,
を得る.
第5問
曲線$y=\log{x}$上の点$\mrm{A}(t,\log{t})$における法線上に,点$\mrm{B}$を$\mrm{AB}=1$となるようにとる.ただし$\mrm{B}$の$x$座標は$t$より大きいとする.
- 点$\mrm{B}$の座標$(u(t),v(t))$を求めよ.また$\Bigl(\dfrac{du}{dt},\dfrac{dv}{dt}\Bigr)$を求めよ.
- 実数$r$は$0<r<1$を満たすとし,$t$が$r$から$1$まで動くときに点$\mrm{A}$と点$\mrm{B}$が描く曲線の長さをそれぞれ$L_{1}(r)$, $L_{2}(r)$とする.このとき,極限$\lim\limits_{r\to+0}(L_{1}(r)-L_{2}(r))$を求めよ.
(1)は微分法の問題で,(2)は曲線の長さを求めるので積分法が絡みます.
解答への筋道
公式が使えればそれほど難しい問題ではありません.
問題の捉え方
曲線$y=\log{x}$上を点$\mrm{A}$が動くとき,点$\mrm{B}$は曲線$y=\log{x}$からやや離れた位置に曲線を描きます.
例えば,点$\mrm{A}$の$x$座標が$r\le x\le 1$を動くとき,点$\mrm{B}$が描く曲線は下図のようになります.
このときの点$\mrm{A}$の描く曲線$L_{1}(r)$と点$\mrm{B}$の描く曲線$L_{2}(r)$は,$r$が0に近いところではどちらもほとんど「まっすぐ」で,長さの差はほとんどないことが見てとれます.
よって,$L_{1}(r)-L_{2}(r)$は$r\to+0$で有限の値に収束しそうで,この極限を求めるのが(2)というわけですね.
グラフの法線ベクトル
関数$f(x)$が微分可能なら,$\ve{d}=(1,f'(t))$は曲線$y=f(x)$の$x=t$での接線ベクトルの1つなので,$\ve{n}=(f'(t),-1)$が曲線$y=f(x)$の$x=t$での法線ベクトルの1つとなります.
本問では$f(x)=\log{x}$なので,$\bra{\dfrac{1}{t},-1}$は$x=t$での法線ベクトルの1つです.
ただし,法線ベクトルは伸縮させても法線ベクトルなので,$t$倍したベクトル$(1,-t)$を法線ベクトルの1つと考えれば,分数がなくなって少し計算が楽になりますね.
いま$|\Ve{AB}|=1$でBの$x$座標は$t$より大きいので,法線ベクトル$(1,-t)$をその長さ$\sqrt{1+t^2}$で割ったものが$\Ve{AB}$となります.
曲線の長さ
媒介変数$t$で表された点$(x(t),y(t))$の描く曲線の長さは,$x(t)$, $y(t)$が共に微分可能なら以下のように積分で求めることができます.
[曲線の長さ(媒介変数で表された曲線)]関数$x(t)$, $y(t)$が微分可能なら,$t$が$a\leqq t\leqq b$を動くときに点$(x(t),y(t))$の描く曲線の長さは
で求まる.
この公式は以下のように考えることができます.
$t$が$t$から$t+\varDelta{t}$まで増加するとき,$\varDelta{t}$が微小なら$x(t)$の増加$\varDelta{x}$と$y(t)$の増加$\varDelta{y}$も微小なので,点$(x(t),y(t))$が描く曲線の長さ$\varDelta{\ell}$は三平方の定理より$\sqrt{(\varDelta{x})^2+(\varDelta{y})^2}$に近似することができます:
よって,両辺を$\varDelta{t}$で割って$\varDelta{t}\to0$とすると
となり,$t$が$a\leqq t\leqq b$を動くときの弧長$\ell$は
となります.弧長の公式の根底に「三平方の定理」があることを理解していれば,この公式は覚えていなくてもすぐに作れますね.
とくに$x(t)=t$, $y(t)=f(f)$とおくと,点$(x(t),y(t))$のグラフは$y=f(x)$となるので,次のように書き換えられますね.
[曲線の長さ(曲線$y=f(x)$)]関数$f(x)$が微分可能なら,$a\leqq x\leqq b$の範囲の曲線の長さは
で求まる.
特殊置換
曲線の長さの公式を用いて$L_{1}(r)-L_{2}(r)$を整理すると
となります.$\dfrac{1}{1+t^{2}}$の積分はノータイムで$t=\tan{\theta}$と置換したいところです.
なお,本問では$L_1(r)$, $L_2(r)$を別々に計算するのは難しく,これらを単独で求めて差をとるという方針では詰まってしまいます.
このように「$L_1(r)$単独,$L_2(r)$単独では難しくても,求められている$L_{1}(r)-L_{2}(r)$は計算できる」といったことはよくあるので注意してください.
解答例
$xy$平面上の原点を$\mrm{O}$とする.
(1) $y=\log{x}$を$x$で微分すると$y’=\dfrac{1}{x}$なので,ベクトル$\Bigl(1,\dfrac{1}{t}\Bigr)$は曲線$y=\log{x}$の点$\mrm{A}(t,\log{t})$での接線ベクトルの1つである.
よって,ベクトル$\Ve{AB}$はベクトル$\Bigl(1,\dfrac{1}{t}\Bigr)$に垂直だから,$\Ve{AB}$は$(1,-t)$に平行である.条件$|\Ve{AB}|=1$と併せて
となる.したがって,
を得る.また,これより
だから,
を得る.
(2) $\dfrac{du}{dt}=t\cdot\dfrac{dv}{dt}$なので,ベクトル$\Bigl(\dfrac{du}{dt},\dfrac{dv}{dt}\Bigr)$の大きさは
である.よって,
である.ここで,$t=\tan{\theta}$($0\leqq\theta<\frac{\pi}{2}$)とすると,
となる.ただし,$\alpha$は$r=\tan{\alpha}$($0\leqq\alpha<\frac{\pi}{2}$)を満たす実数である.
$r\to+0$のとき$\alpha\to+0$であることに注意すれば,
を得る.
第6問
四面体$\mrm{ABCD}$は$\mrm{AC}=\mrm{BD}$, $\mrm{AD}=\mrm{BC}$を満たすとし,辺$\mrm{AB}$の中点を$\mrm{P}$,辺$\mrm{C D}$の中点を$\mrm{Q}$とする.
- 辺$\mrm{AB}$と線分$\mrm{PQ}$は垂直であることを示せ.
- 線分$\mrm{PQ}$を含む平面$\alpha$で四面体$\mrm{ABCD}$を切って2つの部分に分ける.このとき,2つの部分の体積は等しいことを示せ.
空間図形の問題ですね.
解答への筋道
(1)は難しくないので確実に解きたいところですが,(2)は気付けば一発ですがあまりないタイプの問題なのでなかなか気付けないかもしれません.
問題の捉え方
図は以下のようになっています.
直線$\mrm{PQ}$は辺$\mrm{AB}$に垂直であることを示すのが(1)です.確かに,直線$\mrm{PQ}$が四面体$\mrm{ABCD}$の「真ん中」をグサッと貫いているのが見て取れますね.
(2)は直線$\mrm{PQ}$を通る平面$\alpha$は,例えば下図のようになります.
このように,直線$\mrm{PQ}$を通る平面$\alpha$が四面体$\mrm{ABCD}$を2つに分けるわけですが,分けられた2つの部分の体積が等しいことを示すのが(2)です.
断面を考える
空間図形では立体の断面を考えるのが基本です.
(1)は辺$\mrm{AB}$と線分$\mrm{PQ}$を考えるので,断面$\tri{ABQ}$に注目しましょう.
いま$\mrm{AP}=\mrm{PB}$なので,辺$\mrm{AB}$と線分$\mrm{PQ}$が垂直であることを示すには,$\tri{AQB}$が$\mrm{AQ}=\mrm{BQ}$なる二等辺三角形であることを示せばよいですね.
空間上の線対称な図形
(1)より直線$\mrm{PQ}$を軸としてくるくるっと$180^\circ$回転させると点$\mrm{A}$と点$\mrm{B}$は互いに移り合います.
同様に辺$\mrm{C D}$と線分$\mrm{PQ}$も垂直なので,直線$\mrm{PQ}$を軸とした$180^\circ$回転で点$\mrm{C}$と点$\mrm{D}$は互いに移り合いますね.
四面体$\mrm{ABCD}$は線分$\mrm{PQ}$に関して対称な図形になっていることが見て取れます.
よって,線分$\mrm{PQ}$を含むどのような平面$\alpha$で切っても,2つの部分は合同になっており体積が等しいことが分かります.
解答例
(1) $\tri{ABQ}$が$\mrm{AQ}=\mrm{BQ}$の二等辺三角形であることを示せば,点$\mrm{P}$は線分$\mrm{AB}$の中点だから,辺$\mrm{AB}$と線分$\mrm{PQ}$は垂直であることが分かる.
仮定の$\mrm{AC}=\mrm{BD}$, $\mrm{AD}=\mrm{BC}$と,自明な等式$\mrm{C D}=\mrm{DC}$から,$\tri{ACD}\equiv\tri{BDC}$が成り立つから,$\ang{ADC}=\ang{BCD}$を得る.
これと仮定の$\mrm{AD}=\mrm{BC}$, $\mrm{DQ}=\mrm{CQ}$を併せて,$\tri{ADQ}\equiv\tri{BCQ}$が成り立つから,$\mrm{AQ}=\mrm{BQ}$を得る.
以上より,題意が従う.
(2) (1)と点$\mrm{P}$が辺$\mrm{AB}$の中点であることより,点$\mrm{A}$と点$\mrm{B}$は直線$\mrm{PQ}$に関して線対称なので,直線$\mrm{PQ}$を軸とした$180^\circ$の回転で点$\mrm{A}$と点$\mrm{B}$は移り合う.
同様に点$\mrm{C}$と点$\mrm{D}$も直線$\mrm{PQ}$を軸とした$180^\circ$の回転で移り合うから,直線$\mrm{PQ}$を軸とした$180^\circ$の回転で四面体$\mrm{ABCD}$は自身とぴったり重なる.
また,平面$\alpha$は直線$\mrm{PQ}$を含むので,直線$\mrm{PQ}$を軸とした$180^\circ$の回転で平面$\alpha$も自身とぴったり重なる.
したがって,平面$\alpha$によって分割された四面体$\mrm{ABCD}$の一方の部分は,直線$\mrm{PQ}$を軸とした$180^\circ$の回転で,平面$\alpha$によって分割された四面体$\mrm{ABCD}$の他方の部分に移ることが分かる.
したがって,平面$\alpha$によって分割された2つの部分は合同なので,体積は等しい.
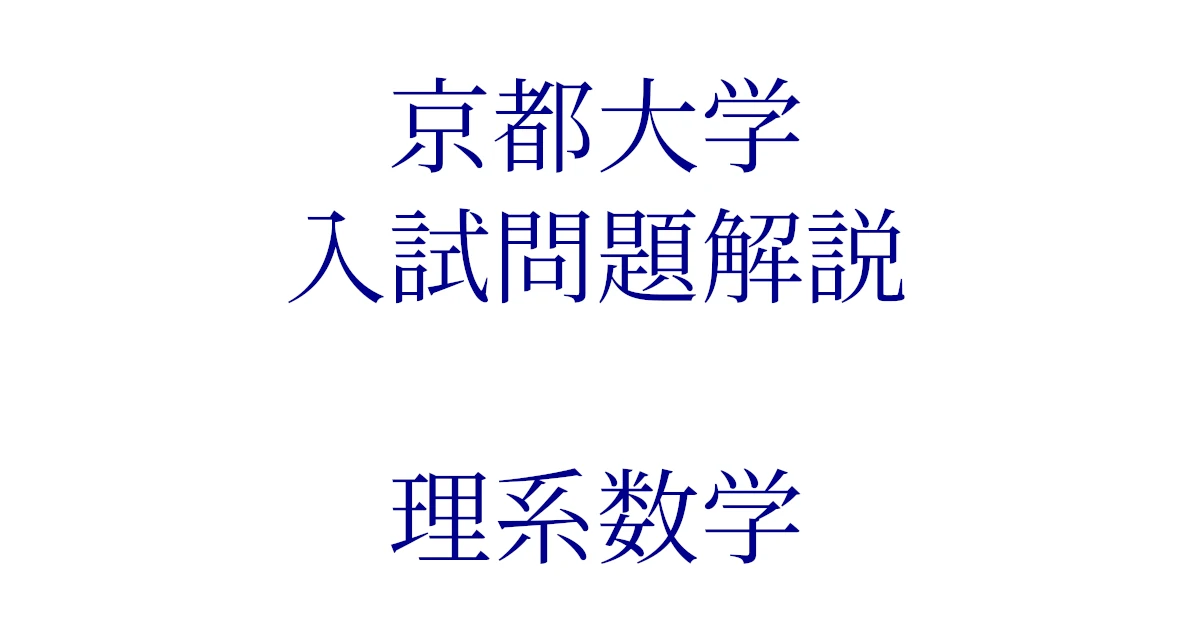
コメント