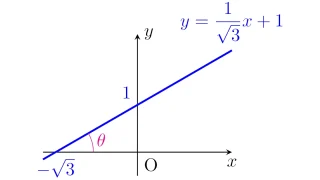 三角比
三角比 tanθの図形的な捉え方|xy平面上の直線の傾きと角度
原点を通る直線とx=1との交点のy座標はtanθとなり,このことからtanθはxy平面上の直線の傾きを表します.この記事では「tanθの図形的な捉え方」「xy上の直線がなす角の具体例」を順に解説します.
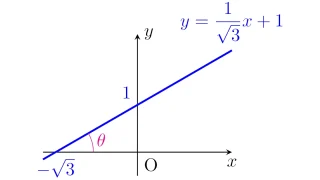 三角比
三角比 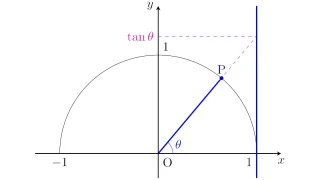 三角比
三角比 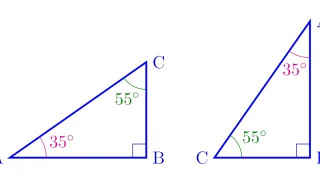 三角比
三角比  三角比
三角比 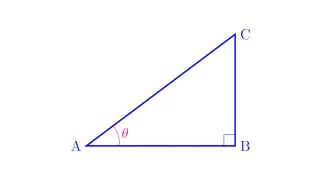 三角比
三角比 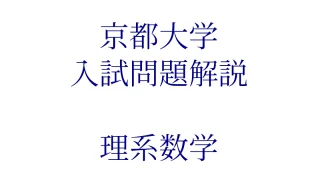 京都大学
京都大学 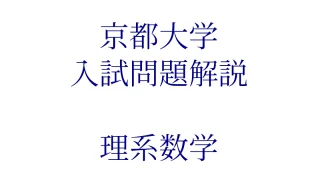 京都大学
京都大学 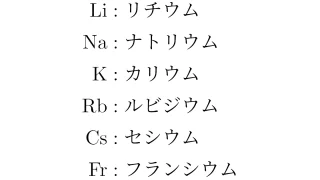 物質の性質
物質の性質  ワンステップ数学
ワンステップ数学 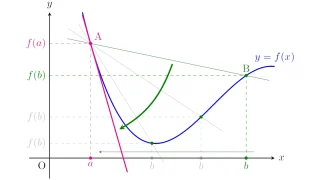 ワンポイント数学
ワンポイント数学